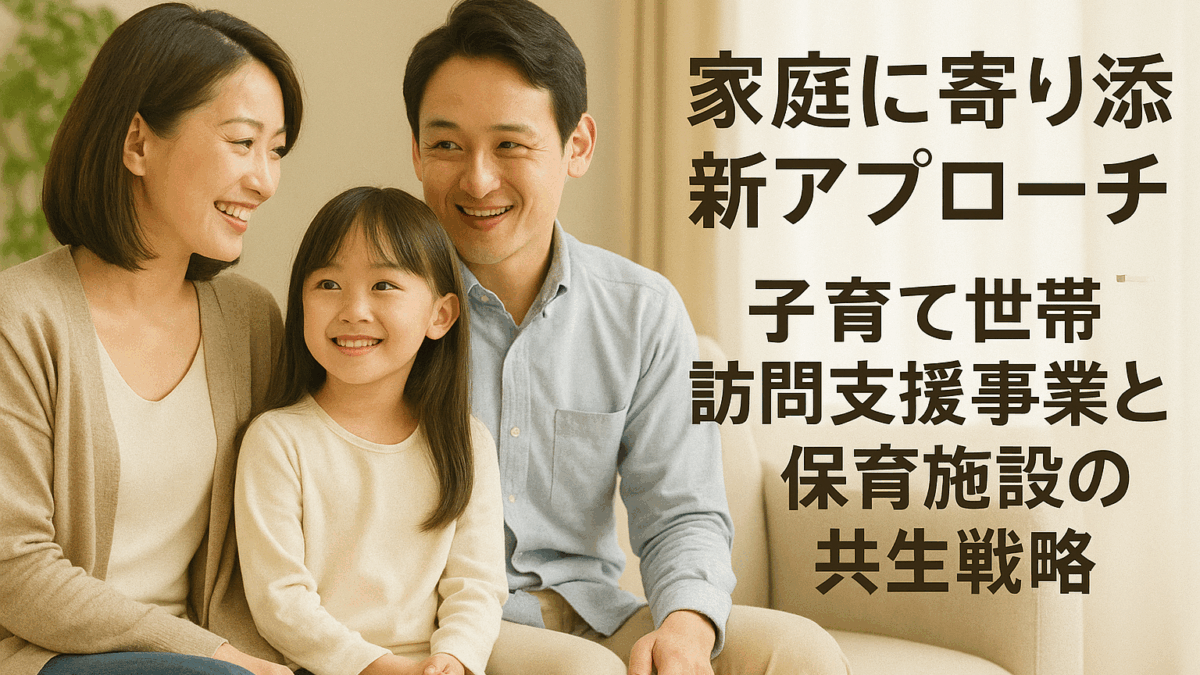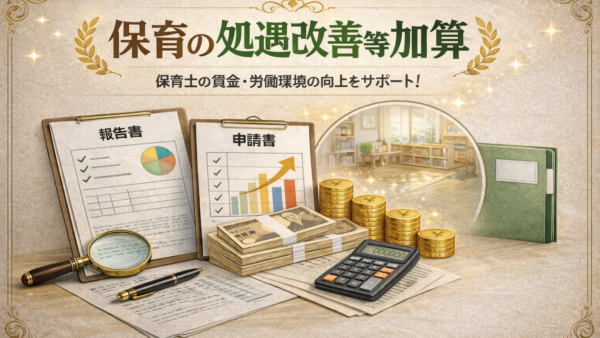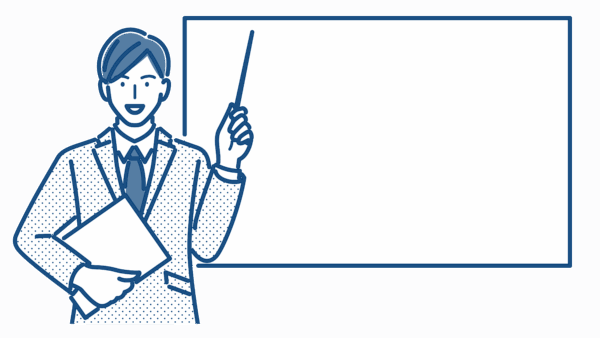◆ はじめに
児童福祉法の改正により、令和7年度から全国展開が本格化した「子育て世帯訪問支援事業」は、育児に不安を抱える家庭へ支援員が定期的に訪問することで、家事・育児の負担を軽減し、育児環境の安定を図るものです。本記事では、保育施設がこの制度をどのように活用し、保育者として関わる意義と実践方法を具体的に解説します。
1. 制度の目的と概要
こども家庭庁が定める本事業の目的は、「家庭支援事業」として、育児の孤立や虐待のリスクを未然に防ぎ、養育環境の改善を図ることです。対象には、育児に不安を抱える世帯、妊産婦、ヤングケアラーなど多様な家庭が含まれます。訪問支援員は、家事・育児の支援や、子ども・親への傾聴を通じた「家庭を元気にする関係づくり」を目的としています。
支援内容は、
- 食事や掃除などの日常家事の支援
- 登園・宿題サポートなど育児支援
- 保護者の悩みに寄り添う傾聴・相談支援
- 支援の必要が高い家庭への情報提供・役所連携
など多岐に渡り、単なる家事代行ではなく、家庭全体の安心と安全を支える包括的支援が特徴です。支援員は自治体が委託し、訪問1時間当たり国・都道府県・市町村それぞれ1/3ずつの補助で運営されます
2. 保育施設として「何ができるか」
◉ 登降園サポートで家庭を安心へ
送迎に支援員が同行できるよう調整すれば、家庭の負担を大きく軽減できます。また、送迎・安全な受け入れ体制を整備することで、支援員と連携した安心運営が可能になります。
◉ 園での育児相談窓口を提供
支援員と保育者が日常的に連携し、園内で育児相談を受け付ける体制を整備すれば、「家庭 →園相談→支援継続」といった支援の恒常化につながります。
◉ 職員の専門性強化・相談対応力の向上
保育者自身がプチ相談窓口を担うことで、支援員との協働が日常化。職員の育児支援スキルが向上し、施設全体の相談対応力が強化されます。
3. 協働体制のつくり方と地域への影響
- 支援員との定期的な情報共有会議を実施し、子ども・家庭の変化情報の共有や対応スケジュールを調整。
- 園が地域支援ネットワークの一員として公認され、自治体との連携強化へ。
- 支援の成果として、園児の安心感向上や園への信頼度向上、さらには虐待早期発見率の向上を期待できます。
4. 実践例:送迎&相談セットプログラム
Step 1:自治体との協議にて「送迎同行+園相談窓口」体制を提案
Step 2:週2回、支援員が園へ同行し、送迎と園内相談対応を併用
Step 3:月1回、園と支援員で支援状況をレビュー、改善策を共有
成果として、家庭の育児負担が軽減され、支援の継続性と効果が向上した事例があります。
5. 行政書士として提供できる支援の範囲
- 自治体への申請・受託支援:支援事業に参加する施設としての制度活用プラン作成
- 契約・同意書の整備:送迎・相談対応に必要な保護者同意書や連携プロトコルの作成
- 運営マニュアル策定:支援員受け入れフローや職員・家庭間の情報共有体制を整備
- 職員研修支援:保育者向けの寄り添い支援研修や協働のルール構築支援
桑園みらい行政書士事務所では、園が制度活用に向けて取り組む際の全過程で、法務・運営・調整をワンストップでご支援いたします。
◆ おわりに
「子育て世帯訪問支援事業」は、保育施設が地域の育児支援ネットワークに深く関わるチャンスです。家庭の孤立を防ぎ、子どもと保護者を継続的に支えるために、保育施設がその中核となるべきです。制度活用と連携によって、施設は地域の信頼を得るだけでなく、職員も成長できる環境づくりが実現します。
📌 出典
- 子育て世帯訪問支援事業ガイドライン(令和6年3月30日)および実施要綱・令和7年予算案 子育て世帯訪問支援事業ガイドライン
- 家庭支援事業について(児童福祉法に基づく総合制度) 家庭支援事業について
- こども家庭庁 子ども・子育て支援交付金 子育て世帯訪問支援事業