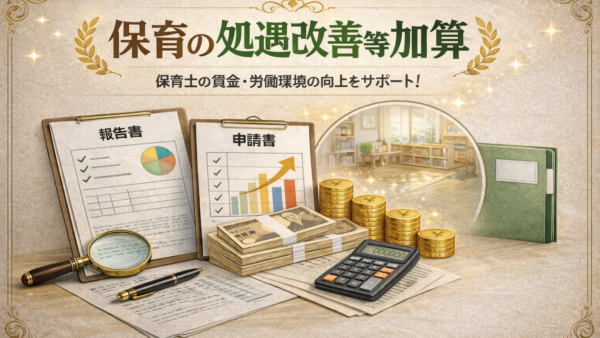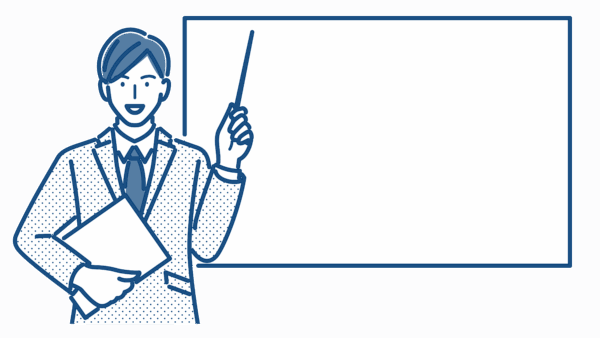◆ はじめに
少子化や共働き家庭の増加により、子どもが安心して過ごせる「居場所」のニーズは高まっています。こども家庭庁は令和7年度、「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」などを通じて、放課後児童クラブやこども食堂など、地域で子どもを支える仕組みを重層的に支援。今回は、保育施設・保育者がどのように関わり・活用していくべきかを整理します。
1. 制度の全体像と関与の視点
こども家庭庁が拡充した3制度は、①支援体制強化、②コーディネーター配置、③放課後児童クラブ強化です。これらは自治体主導ですが、保育施設としては「運営資源の提供者」や「地域支援者」として関わることができます。
たとえば「支援体制強化事業」では、施設が地域調査・広報配布・居場所マップ作成を共同実施する受託先になることで制度利用の立役者として位置づけられます。
2. 放課後児童クラブ強化パッケージとの連携
放課後児童クラブに関する「2025パッケージ」では、施設側も協働の担い手として位置付けられています。特に「保育所等の積極的活用」は、地域型保育園などの放課後解放や施設提供を促進する意図が明記されており、保育園が場所提供や一時預かりスペースを担う重要なロールを担います
また「ICT化推進」では、職員の記録業務負担軽減に貢献できる姿勢が、現場の信頼度を高める一環となります。
3. こども食堂・地域型居場所への関わり方
自治体やNPOが主導するこども食堂では、保育施設が以下の方法で関与できます:
- 会場提供者として週1回スペース提供
- 職員の人的支援:見守りやイベント運営のサポート
- 広報連携:保護者宛案内やSNSでの情報共有協力
こうした関与により「地域の信頼」や「子育て支援の拠点」というイメージが形成され、保護者との接点強化にもつながります。
4. コーディネーター配置事業との協働
制度では自治体配置のコーディネーターが地域事業をつなぎますが、保育施設は「事業パートナー」として協働の役割があります。施設側からニーズや課題を共有し、運営会議や定例に参加することで、実効的な連携体制を築けます。
この関与の中で、法的整備や施設ガイドライン作成など、行政書士としても支援も可能です。
5. 夜間・災害時・長期休暇期の居場所対応
制度には「災害時・一時避難的居場所の確保」も含まれ、夜間見守りや宿直体制への対応経費が計上されています 内閣官房。保育施設が防災拠点や避難所の一部として機能できるよう、拠点協定や運営計画を自治体と共同で整備しておくことが求められます。
6. 実践プラン例:保育園が担う放課後学び場モデル
- 自治体・コーディネーターと会議を実施し役割を整理
- 園舎内に放課後学習スペースを試験設置
- 職員と連携し週2日程度の解放プログラム実施
- 運営協議会で補助金申請や広報計画を策定
- 自園リソースを活用しながら、自治体と連続支援を展開
このモデルにより、子どもの居場所が提供されるだけでなく、職員の地域支援参加が職務として明確化することになります。
7. 行政書士としての支援ポイント
- 制度利用計画の策定支援・補助金申請代行
- 自治体・NPO・園との調整支援
- 場提供契約書・運営規定・保護者同意書類の整備
- 災害時運営に関する法的対応サポート
8. まとめ
令和7年度の居場所支援制度では、保育事業者がただ「場を提供する」だけではなく、協働体制の一員として中核的役割を担うことが期待されています。地域に根差した子どもの安心環境づくりに貢献するために、制度の活用や連携体制の構築を今こそ検討すべき時です。
桑園みらい行政書士事務所は、条例整備から運営ルール作成、補助金申請まで、包括的なサポートを提供します。子どもにとって安心できる「第3の居場所」をともにつくっていきましょう。お気軽にお問い合わせください。
📌 出典(こども家庭庁・文部科学省公式資料)
- こども家庭庁「こどもの居場所づくり支援体制強化事業について」「災害時のこどもの居場所づくり」こども家庭庁
- こども家庭庁・文科省「放課後児童対策パッケージ2025」 放課後児童対策パッケージ 2025
- こども家庭庁・「放課後児童対策パッケージ2025」 厚生労働省