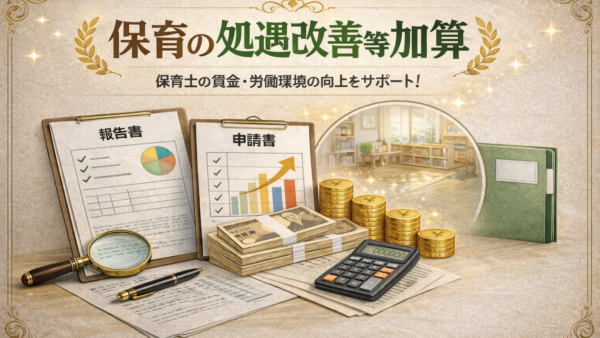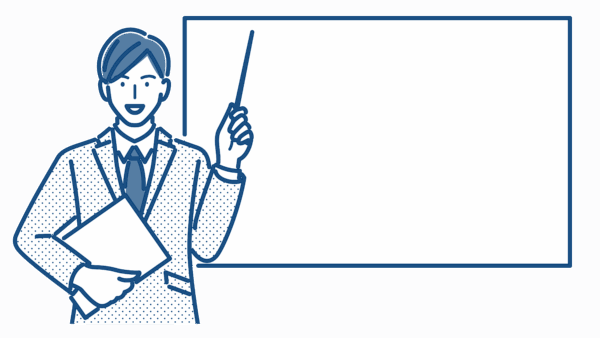令和7年度から全国で拡大される「子ども誰でも通園制度」、保育事業者として本制度の導入を検討するにあたり、現場対応の準備と運営リスク理解は必要不可欠です。本記事では、制度の概要から、保育園・こども園等事業者にとってのメリット・デメリット、そして対応策までを整理して解説いたします。
1. 制度概要
- 対象:0歳6ヶ月~満3歳未満で保育所等に未登録、既存実施施設も含む
- 利用枠:月10時間(自治体裁量あり)
- 契約:市町村と施設の直接契約。一般事業型のみ、保険加入や報酬補助要件あり
2. 保育事業者にとっての3大メリット
✅ ① 利用者拡大・定員対策に効く
- 定員割れの解消に期待でき、利用率の向上につながる
✅ ② 新規参入しやすい制度設計
- 既存の認可・地域型施設が対応可能で、他の保育サービスとの差別化に好機
✅ ③ 障がい児や医療ケア児への加算支援あり
- 障がい児受入れ等への加算制度が整備されており、適切な支援体制整備にあたって重要な収入源となる
3. 保育事業者の運営面から見たデメリット
⚠️ ① 短時間利用による業務負担増
- リズム・アレルギー把握や安全管理などが複雑化し、スタッフの事務・保育ともに負担増
⚠️ ② スタッフ確保の課題
- モデル園では「81.6%が保育者確保難」と回答。特にパートなど柔軟体制が求められる
⚠️ ③ 請求・記録の煩雑化
- 在園児と制度利用児の請求・記録ルールが異なり、二重管理の必要性から事務工数が増加
⚠️ ④ 事故リスクの増加
- 短時間保育はアレルギー・事故のリスクが高く、補償保険加入など体制整備が必須
4. 具体的対応策と現場事例
| 課題 | 対応策・現場事例 |
|---|---|
| 今後増える短時間利用児 | シフト・パート体制の柔軟化(モデル園の工夫) |
| 保護者対応の増加 | 写真付きコメントやカードによる情報共有 |
| 請求・記録管理の二重化 | ICTツールによる一元管理(入退室・請求・連絡帳) |
| 安全対応と事故リスク | 午睡センサー導入や賠償保険加入 |
5. 制度が必要とされた背景
- 核家族化や孤育ての増加:親の孤立感が深まり、育児ストレスが社会問題に
- 就労条件に左右される保育制度:従来は「働いていないと利用できない」という制度の壁が存在
- 乳幼児期の社会性発達の重要性:3歳未満からの集団生活が、発達や情緒面にも良い影響
こうした背景を受け、政府は「すべての子どもに質の高い保育の機会を提供する」ことを目指し、令和7年度より本制度を正式導入しました。
6. おわりに
「子ども誰でも通園制度」は、制度の壁に阻まれてきた多くの家庭にとって、まさに希望となる制度です。
施設側にとっても、新たなニーズに応える柔軟な運営モデル構築の機会となります。
桑園みらい行政書士事務所では、本制度の活用に関する申請・相談支援を行っております。お気軽にご相談ください。