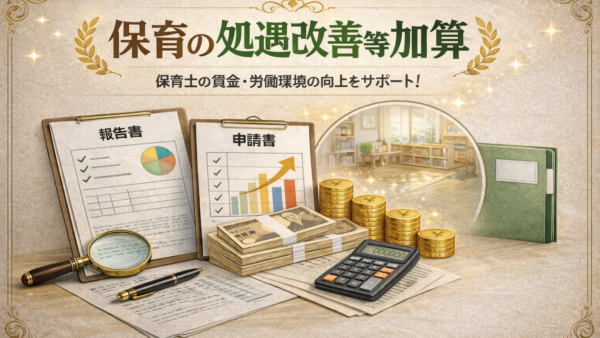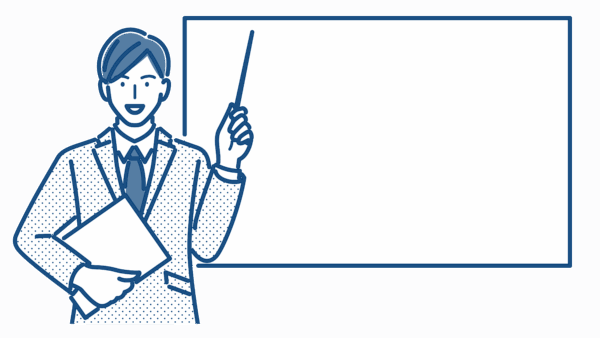選定評価基準の詳細と通過のポイント(設備・支援内容・運営体制)
選定制度では、設備・人員、個別支援内容、運営計画・継続性、職員研修や処遇改善など、複数の評価軸によりスコア評価されます。以下に要点を整理します。
設備・人員
- 小学校区単位で児童数と既存事業所数のバランスが評価対象となるため、過密地域はハードルが高くなります。
- 指導訓練室の面積は児童1人当たり2.47㎡以上であることが必要です。また、相談室や事務室などの個別対応スペースも必ず確保してください。
- 管理者や児童発達支援管理責任者(児発管)は常勤かつ専門性を備えていること。児発管研修修了や実務経験のある職員配置が評価されます。
支援内容と個別支援計画
- 支援内容確認書やアセスメント結果に基づいた個別支援計画の具体性が審査に大きな影響を与えます。支援目標やモニタリング方針が明確に記載されていることが求められます。
- 家族支援や地域連携体制(児童発達支援センターや相談支援機関との協働、保育所等訪問支援の計画)も加点対象となります。
運営体制と継続性
- 過去の事業運営実績、財務計画の健全性、人材育成方針などを提出することで信頼性をアピールできます。
- 危機管理体制(非常災害対策など)や職員研修スキーム、処遇改善への取組も評価対象です。
申請後、選定通過した内容(特に管理者や施設位置など)の変更は原則認められないため、初期段階での慎重な計画が不可欠です。
指定取得後の義務と運営管理体制の整備
指定取得後は、札幌市や北海道庁が行う監督体制に則り、以下の義務を継続して遵守する必要があります。
個別支援計画の策定と定期的見直し
児童発達支援管理責任者が作成した支援計画は、6か月ごとのモニタリングと見直しが求められます。達成状況を記録し保護者へ説明し、同意を得るプロセスを確保してください。
帳票類や記録の整備
契約書、事故報告書、提供記録、苦情記録、重要事項説明書などを整備し、保存期限に従って保存します。
加算取得体制の維持
児童指導員加配加算、送迎加算、医療的ケア加算などを利用する場合、常に要件を満たす職員配置・記録体制を維持し、変動時には届け出を行う必要があります。
実地指導への対応
指定後1年以内に初回の実地指導が行われ、その後も定期的な指導が継続されます。是正事項がある場合は迅速に対応しないと指定取消に至る可能性もあります。
指定の更新申請
指定有効期間は6年ですので、有効期限満了前に更新申請を行い、引き続き運営できるよう所定の書類を提出してください。
ケース別の注意点とリスク回避策
保育所の空き教室を活用する場合
- 建築基準法に基づく用途変更や市街化調整区域での制限を確認してください。
- 消防法上の防火対象物使用開始届出(開所4日前まで提出)や避難経路の確保も必須です。
- 指導室や相談室の面積が基準を満たしているか事前に測量・確認をおすすめします。
医療的ケア児を受け入れる際
- 看護師や嘱託医を配置し契約書や記録体制を整えることが必須です。また、医療的ケア加算の届出準備も併せて行いましょう。
法人格や定款、人員不足のリスク
- 定款に必要な記載がない、児発管の資格や実務経験が不足している場合、申請は受理されません。早期の準備が重要です。
年度募集漏れで申請できないリスク
- 選定募集期間を逃すと翌年度まで申請不可能になり、事業開始が1年以上遅れる可能性があります。
今後の国制度動向とこども家庭庁の施策展望
厚生労働省による「障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書」では、支援の質評価指標の導入や制度透明性の向上、福祉型と医療型の制度統合が示されており、今後の制度変更の方向性が明らかになっています。
こども家庭庁においても、改正児童福祉法に基づく制度見直しや地域支援体制の強化、報酬改定などが予定されており、今後、指定申請書類や支援計画フォーマットの変更も予測されます。
以上を踏まえ、制度改正への柔軟な対応力や継続的な行政情報のキャッチアップが重要になります。