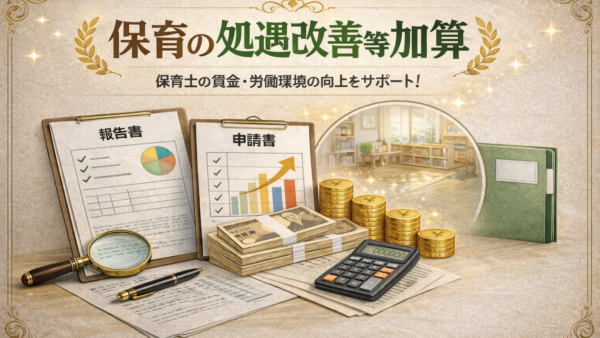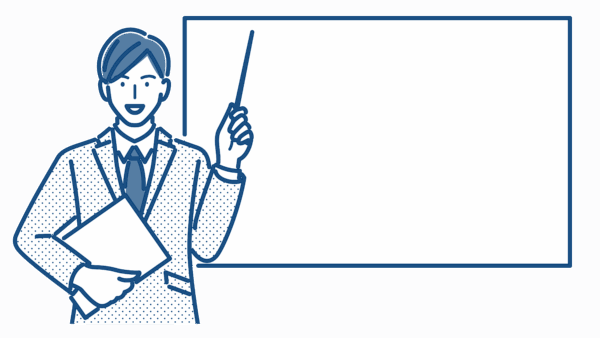第1章:制度導入の背景と選定制度の全体像
札幌市では、児童発達支援施設や放課後等デイサービスの過剰な拡大に伴い、サービスの質維持と供給の適正化を目的として、令和7年4月1日から国基準に加え独自選定基準を設定する選定制度を導入しました。指定申請にはまず市が公表する募集期間中に選定申込を行い、選定通過=指定申請の権利獲得という構造に変更されています。選定されなければ、開設自体が翌年度に持ち越されるため、「選定に受かる」ための準備が不可欠です。
第2章:「指定申請 流れ 要件」をわかりやすく解説
以下の表は、札幌市における令和7年度指定申請の全体的なスケジュールと流れを整理したものです。
| ステップ | 内容 | 実施時期(目安) |
|---|---|---|
| 1 | 事前相談・構想提示(物件、人員、計画等) | 開設希望の3か月前 |
| 2 | 選定申込書提出(公募期間内) | 4月下旬~6月30日 |
| 3 | 選定結果通知(委員会審査) | 7月下旬頃 |
| 4 | 指定申請書提出(選定通過者のみ) | 8/1~翌7/末 |
| 5 | 書類審査・必要時現地確認 | 約1か月以内 |
| 6 | 指定通知受領・開設準備開始 | 指定日より6年有効 |
札幌市では開所希望日の2か月前までの事前予約が義務付けられており、申請後約1か月で正式指定通知が出される流れです。
第3章:法人格と定款記載の完備が重要な理由
指定申請主体は株式会社・社会福祉法人・NPO法人等の法人格を有することが必須です。個人事業主は対象外。さらに、定款に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」の記載があることが絶対条件。定款の目的欄に記載漏れがあると不受理となるため、法人設立時または定款変更時に確実に対応すべきポイントです。
第4章:人員配置要件の実務的詳細
管理者と児童発達支援管理責任者(児発管)
- 管理者:常勤1名以上(兼務可)
- 児発管:専任・常勤1名以上。実務経験と研修修了証の提出が要件。
この児発管は、個別支援計画の策定、見直し、保護者との連携などを統括する役割であり、指定時の最大の要件厚です。
指導員・保育士等
- 定員10名の場合、常勤換算2名以上配置し、そのうち半数以上は資格保持者であることが必要。
- 非常勤のみでは基準不充足となります。
医療的ケア児対応
- 医療的ケア児を受け入れる場合、看護師や嘱託医との契約書や記録体制の整備が要件として求められます。
第5章:施設基準と消防法・建築基準法との適合
面積・構造要件
- 指導訓練室は児童1人当たり2.47㎡以上。10名なら24.7㎡以上の広さが必要です。
- 相談室、事務室、静養室など個別対応スペースの整備も必須。
- “保育所 空き教室 発達支援 施設 開設 手続き”では、用途変更や区分用途適合性の確認が重要です。
衛生・安全設備
- トイレ、手洗い場などの衛生設備の確保。
- 消防署への防火対象物使用開始届出書を使用開始4日前までに提出し、避難経路・消火器・自動火災報知機などを適切に設置する必要があります。
- 古い建物の場合は検査済証の有無も確認対象となります。
第6章:提出書類一覧と整理ポイント
指定申請に必要な書類は30種類以上あり、主な資料を以下にまとめました。
- 指定申請書・チェックリスト様式
- 法人登記事項証明書・定款写し
- 平面図・施設写真・付近地図
- 管理者および児発管の経歴書・研修修了証
- 職員配置図・勤務表・運営規程・苦情処理体制
- 事業計画書・収支予算書・設備備品一覧
- 賃貸借契約書写し・損害保険証明・医療機関契約書
- 加算届出関係体制届出書
- 正本・副本両方を整え、順序正しくインデックス付きで整理
提出前には提出書類チェック表で記入漏れがないか必ず確認を。
第7章:選定評価基準と通過率アップの要点
札幌市の選定制度では、以下の複数観点によるスコア評価が行われます。
- 設備・人員:常勤職員数や職員経験・専門性など
- 支援内容:個別支援計画の策定内容、意思決定支援のプロセス
- 家族支援・地域連携:保護者支援や相談支援拠点との連携
- 収支の安定性:実行可能な収支計画と資金調達能力
- 職員育成・待遇環境:研修制度や処遇改善への取組
選定通過後の内容変更(管理者交替・施設変更など)は原則不可.最初の計画がそのまま選定基準となります。
第8章:指定取得後の義務と運営管理
指定取得後も、以下の運営義務を確実に遂行する必要があります。
- 個別支援計画の策定と6か月ごとの見直し
- 提供記録、契約書、事故報告書等の帳票類の整備・保管
- 加算管理体制を維持し、変更届出を適時提出する
- 定期的な実地指導対応:指定後1年以内に初回、その後も定期更新
- 指定更新申請:指定有効期間6年の満了前に更新手続きを実施
違反や記録不備がある場合は、是正指導や最悪の場合指定取消のリスクがあります。
第9章:今後の国制度の動向と福祉施策の方向性
最新制度動向では、こども家庭庁の主導により、「地域支援体制整備」「ガイドライン改訂」「医療的ケア児支援の制度統合」などが進行中です。令和6年度報酬改定に伴い、個別支援計画の書式見直しや加算要件の整理、ICT補助の追加も行われています。
厚生労働省の検討会では、支給決定プロセスの透明化や支援の質評価指標体系の導入が議論されており、近い将来、指定申請書類や計画書の記載要件が改訂される可能性があります。