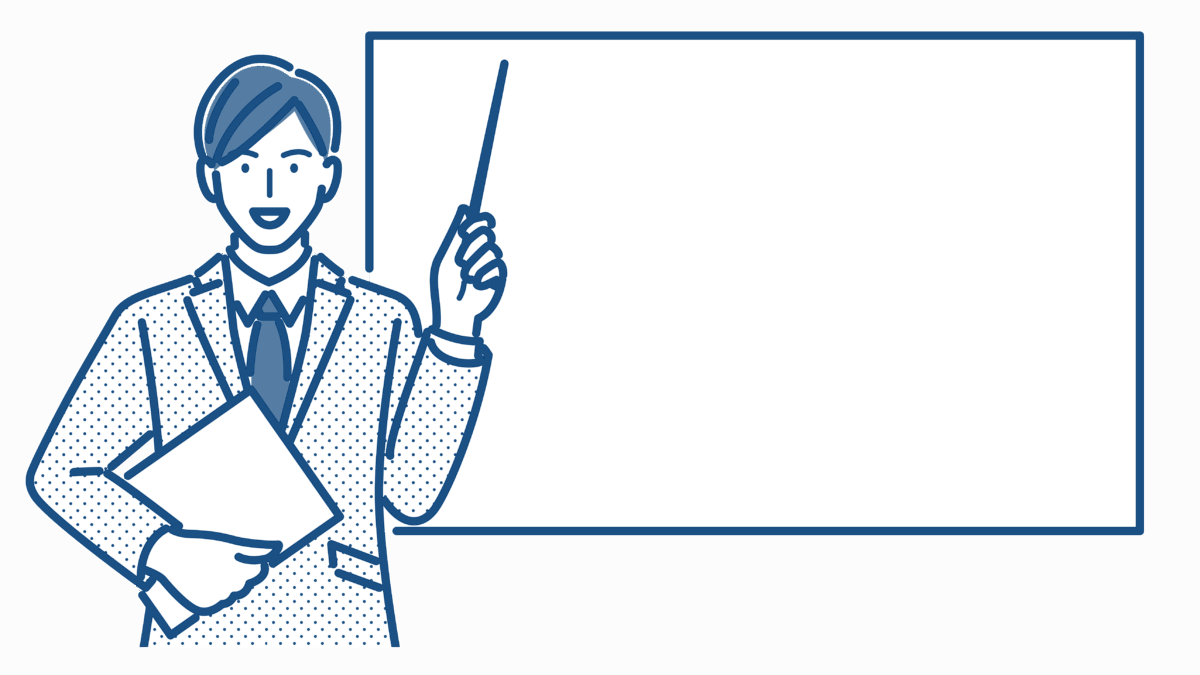処遇改善加算とは?
「処遇改善等加算」とは、認定こども園、保育所、幼稚園などの特定教育・保育施設や特定地域型保育事業所において、職員の賃金改善やキャリアパスの構築、資質向上への取り組みを促進するために給付費に加算されるものです。これにより、保育現場で働く職員の待遇を改善し、質の高い教育・保育を安定的に提供できる体制を確保することを目指しています。
この加算は、施設型給付費の「基本分単価」に加えて支給される「加算額」の一部であり、主に人件費の改善に充てられます。
処遇改善加算の主な区分と目的
処遇改善等加算には、主に以下の3つの区分があります。
1.区分1(基礎分):
目的: 職員の職位、職責、職務内容に応じた勤務条件を定めている施設に加算されます。
算定方法: 施設における職員一人当たりの平均経験年数に応じて、加算率が変動します。
1年未満: 2%
1年以上2年未満: 3%
2年以上3年未満: 4%
3年以上4年未満: 5%
4年以上5年未満: 6%
5年以上6年未満: 7%
6年以上7年未満: 8%
7年以上8年未満: 9%
8年以上9年未満: 10%
9年以上10年未満: 11%
10年以上: 12%
備考: キャリアパス構築要件は、旧加算Ⅰ(賃金改善要件分)の未構築時の減率が廃止され、職場環境改善を進める観点から区分1の要件として設定されました(1年間の経過措置あり)。
2.区分2(賃金改善分):
目的: 賃金改善の実施計画を策定し、賃金改善に取り組む施設に加算されます。
算定方法: こちらも職員一人当たりの平均経験年数に応じて加算率が設定されます。
11年未満: 6%
11年以上: 7%
賃金改善の方法: 基本給の引き上げや手当の創設、一時金の支払いなど、賃金改善の項目は特定した上で、毎月払い、一括払いなどの方法で改善を行うことが可能です。ただし、基本給の引き上げや定期昇給の増額など、段階的に反映していくことが望ましいとされています。処遇改善等加算は、定期昇給とは別の「上乗せ」として賃金改善を行う必要があります。
3.区分3(質の向上分):
目的: 技能と経験を有する職員(副主任保育士等や職務分野別リーダー等)に対して、追加的な賃金改善を行う場合に加算されます。
対象者: 副主任保育士等や職務分野別リーダー等が対象です。年度内に研修修了を予定している者で、準ずる職位や職務命令を受けている者も対象に含まれます。
賃金改善の方法: 役職手当、職務手当など、職位・職責・職務内容に応じて、毎月支払われる手当または基本給により改善を行うこととされています。
配分の柔軟化: 月額4万円の改善分について、施設判断により柔軟な配分が可能となりました。職務分野別リーダー等には、副主任保育士等に対する改善額のうち最も低い額を上回らない範囲で、5千円以上4万円未満の改善額とすることができます。
算定の基本的な考え方と留意事項
公定価格の構成: 施設型給付費は、「基本分単価」と「各種加算」で構成されます。地域区分、定員区分、認定区分、年齢区分に応じて基本分単価が定められ、処遇改善等加算はこの基本分単価に加算されます。
市町村の役割: 公定価格は市町村が設定しますが、基本的には国の標準価格に基づいて設定することが求められています。
賃金改善額と加算額の関連: 基準年度を起点として、職員の賃金改善額が加算額の増加分以上であることが求められます。
半額ルールの適用: 区分2および区分3を合わせた加算による改善額のうち、2分の1以上は基本給または毎月支払われる手当による改善でなければなりません。制度変更に伴い認定が遅れた場合でも、原則として速やかにこの要件を満たす必要があります。
残額の扱い: 加算年度の終了後、賃金改善によって残額が生じた場合は、翌年度内に速やかにその全額を一時金等で支払い、職員の賃金改善に充てることとされています。
賃金改善の報告と記録: 区分2および区分3の適用を受けた施設は、賃金改善に係る収入と支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、実績報告後5年間保管する義務があります。
適用優先順位なし: 各加算の適用に優先順位はなく、各園の実情に応じて必要な加算を選択できます。